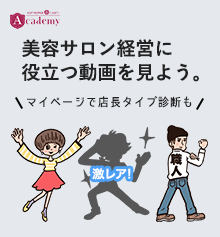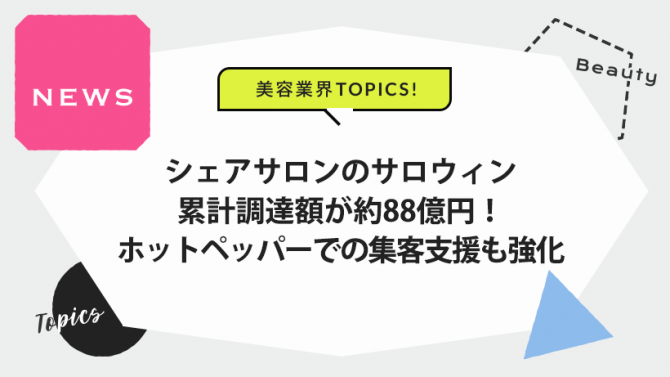2011.12.14
2011年3月11日に起きた東日本大震災以降、あらゆるものの価値や本質が問われています。前リッツ・カールトン日本支社長の高野登氏が提言するホスピタリティの重要性は、3.11後の美容業界が求められている課題への、ひとつの解答とも言えるかもしれません。お客さまと企業が共鳴し、ブランドという価値を作り上げていく “本物の組織”の真髄を、高野氏の言葉から感じ取ってください。
PROFILE

高野 登(たかの のぼる)
1953年、長野県生まれ。プリンスホテルスクール(現日本ホテルスクール)第一期卒業。1974年渡米。ニューヨーク(NY)・ホテルキタノ、NYプラザ、LAボナベンチャー、SFフェアモントなどでの勤務を経て、1990年にザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコの開業に携わる。1992年に日本支社開設のため一時帰国。1993年にはホノルルオフィスを開設。翌94年、日本支社長として転勤。リッツ・カールトンの日本における営業・マーケティング活動を行いながら、ザ・リッツ・カールトン大阪の開業準備に参画。2007年3月のザ・リッツ・カールトン東京の開業後は、さらにポジショニングを強化すべく、積極的にブランディング活動に取り組む。2009年9月、退社。2010年1月、人とホスピタリティ研究所設立。現在に至る。
|第2章|強い絆で結ばれたお客さまと、夢と物語を紡ぐ
リッツ・カールトンが捉えているホスピタリティ、おもてなしの原点とは何か。それは、「スタッフ一人ひとりがお客さまとの絆を作り、お客さまの夢を一緒になって積み上げていくこと」です。フロント、ドアマン、メイド、ウェイターと、それぞれが担う役割によっておもてなしの表現方法は異なるけれど、すべてはこの一点に集約されます。「どのようにお客さまにお金を払ってもらい、会社の収益を上げるか」ということは、誰一人考えていません。なぜなら、会社の収益を上げるのは簡単だから。お客さまが来てくれて、財布を開いてくれれば、それで十分ですよね。
では、どうすれば財布を開いてくれるのか。お客さまは商品そのものではなく、これらに付随した夢に対してお金を払っているのです。モノとしては誰が売っていても、どこで買っても同じはずなのに、Aの店で買いたい、Bの店には行きたくない、ということがありますよね。お客さまがどんな夢や物語を求めていて、何を欲しているのか。それをスタッフが理解しているかどうかが、この差に現れてくる。お客さまの夢へ真剣に向き合い、「必ず実現してあげよう」という思いをスタッフ一人ひとりが真摯に抱くことがホスピタリティの基本であり、そのためには、信頼関係に基づいた強固な人間関係をお客さまと築いていくことが、何よりも必要なのです。
先日、ある会社の入社式にお招きいただいた際に、心に残るエピソードを伺ったので、みなさんにお伝えしたいと思います。
その会社というのは、しゃぶしゃぶを中心とした日本料理で知られている外食チェーン企業の「木曽路」で、入社式と併せて、優秀な店舗に賞を授与する表彰式が本社で行われました。3.11以降、外食産業は軒並み痛手を被っていますが、木曽路も苦戦を強いられていたんですね。しかし、この状況の中で、なぜか前年より売り上げを伸ばした店があった。私はその訳を知りたくて、表彰された店長にインタビューをしました。詳しく話を聞いてみると、その店では3.11の直後、被害を受けたお客さまに援助を申し出たというのです。あり合わせのもので作った食事を提供し、「店にはまだ食料があるので、足りないものがあったら遠慮なく言ってください」と電話をかけ、電話が通じない人には、人づてで住所を聞いて直接家を訪ねていった。そして震災がひと段落したころ、「あの時に声をかけてもらって本当に安心できた」と、常連さんが新しいお客さまを連れて店に帰ってきてくれたのだそうです。「いつものお客さまに支えられただけなんです」という店長の言葉が、とても印象的でした。
もし彼らが、キッチンで作った料理をテーブルに運ぶだけの仕事しかしていなかったとしたら、これほど確かな人間関係をお客さまと結ぶことはできなかったでしょう。店に訪れるカップルやファミリーにとっての夢や物語を、本気になって、お客さまと一緒に紡いでいく努力を続けてきた。だからこそ震災後の不況下で、前年よりも売り上げを伸ばすという奇跡を達成することができたのだと思います。